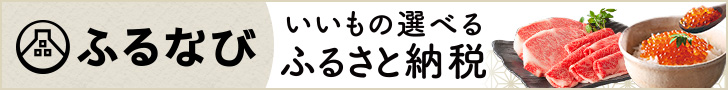古典落語「一文惜しみ(いちもんおしみ)」
 【あらすじ】
【あらすじ】
神田三河町の裏長屋にくすぶる初五郎は博打場の使い走り。長患いを機に、やくざ家業に縁を切ろうと大家を訪ねた。「堅気になって八百屋でもやろうかと思って、ちと相談を」「商売には元手が要る。奉加帳(ほうがちょう)をこさえてやるから、心安い金持ちを当たるといい」
初五郎が思いついたのは同町内の徳力屋万右衛門という質屋だが、主人の万右衛門は大変なしみったれ。奉賀帳に付けた金額はわずか一文。
「乞食じゃねえんだ、一文ばかりいらねえや」畳に叩きつけた銭が跳ね返って万右衛門の顔にぶつかる。手元の煙管で受けた拍子に雁首(がんくび)が初五郎の額に当たって血が流れ出した。
訳を聞いた大家は、奉行所への駆け込み訴えをさせた。両者の言い分を聞いた時の南町奉行大岡越前守は、傷を負わせた万右衛門にはお咎めなし、初五郎には商売の元手として五貫文を貸し与えるというお裁きを下した上、返済は一日一文ずつ。返済金の取次を任された徳力屋は、おやすい御用と喜んだ。翌朝から早速初五郎が一文返しに来ると、手すきの手代が奉行所に届ける。
すると「貸し与えた節は名主五人組立ち会いである。帰って連れてこい」。驚いた万右衛門は名主、五人組を頼んで奉行所へ。
この礼金が痛手になり三日で音をあげた万右衛門は、初五郎へ十両やって示談にしたほうが安いと算段。初五郎は喜んだが大家は「千両びた一文まからない」と大見得を切る。一割の百両にまけてくれと懇願されて、示談成立というお噺。